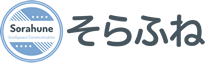レゴセラピー
レゴセラピーは、レゴブロックを使った遊びを通して、お子様の発達を総合的にサポートする、そらふねの中心となる療育法です。


ブロック遊びで育む6つの力
1. 集中力と記憶力
ブロックを組み立てるときの基本動作の、「つまむ」「はめる」「外す」の3つの動作は大脳を活性化させます。大脳は言語能力や運動能力などを司っており、ブロックを組み立てては壊し、ふたたび組み立てる…。ということを繰り返すことで、集中力や記憶力が向上するといわれています。
2. 手先が器用になる
ブロック遊びには、手先の巧緻性(手先の器用さのこと)を高める効果があります。「自分が作りたいものを組み立てる!」言葉にすると簡単に思えますが、手先の動きにまだ慣れていない子どもたちにとっては、実はとても大変なことなんです。 子どもたちが自分の思うような形を作るため、トライ&エラーを繰り返しながら指先を動かすことで、自然と手先の器用さが身についていきます。
3. 空間認識能力の向上
空間認知能力とは、物体の形状や位置、大きさ、向いてる方向、自分自身との位置関係を察知する力です。ブロックを組み立てるには、平面だけでなく、幅・高さ・奥行・物の向きなど立体的に物を捉える力が必要になります。そのため、子ども達はブロックを組み立てている時や完成したときに色々な角度から観察したり、遊んだりして空間を把握する力を育んでいきます。
4. 発想力や創造性を育む
ブロックは、興味・関心が高いものを自由に組み合わせて作ることができ崩せばまた一から作り直すことができます。 そんな特長の楽しさを、子どもたちが感じとれるようになることで、能動的に自分の世界観をブロックで広げられるようになっていきます。そして、お友達と一緒に作っていくことで「次は〇〇してみよう!」「〇〇ができるんじゃない?」と多角的な発想から独創的な作品を作りあげることも珍しくありません。ブロック遊びの正解は、子ども自身のなかにしか存在しません。ゆえに明確な目標やゴールがありません。それが子供の探求心を刺激し「もっと〇〇できるようになりたい」「〇〇なものを作ってみたい」という欲求に繋がると考えられています。
5. 自己肯定感が高まる
作品が完成するたびに得られる達成感は、子供の自己肯定感を育みます。自己肯定感は成功体験の積み重ねで形成されるため、一朝一夕では育ちません。したがって楽しくブロック遊びを続けることで自己肯定感を高めていくのは、療育の観点からも有効といえます。
6. 協調性とコミュニケーション能力
保護者やきょうだい、お友達など、幅広い世代と遊べるのもブロック遊びの特徴です。他者が作っている作品や自分が作っている作品を共通の話題にしたり、協力して一緒に作品を作ったりすることで、協調性やコミュニケーション能力を高めていくことができます。コミュニケーション能力は、日々の積み重ねから徐々に身についていくものです。特に幼児期は、コミュニケーションの基礎を作る時期になります。お友達や色んな年代の人とのやり取りができるブロック遊びはコミュニケーション能力を育むにも大変有効です。
取り組みの例
- 「色分けや形分けにより、概念への理解を深める」
- 「自由な発想で、空間認識能力や創造性を育む」
- 「仲間と一つの作品を作ることで、協力することの大切さや社会性を学ぶ」
遊びを通して学び、心身ともに成長できる機会を与えます。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)

ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは、社会で生活していくためのスキルを習得するための訓練のことです。
障がいのあるお子様は、集団内での行動の善し悪しを周りの様子から推察したり判断することが苦手で、注意をされてもなお同じことを繰り返してしまうことがあります。
そらふねでは、一人ひとりの発達段階に応じたSSTを実施していきます。
取り組みの例
ゲームのルールが守れるようになるという目標に対して
- 「ゲームは負けることもあるということを知る」
- 「負けても楽しいという感覚を身につける」
- 「悔しくても自分の感情をコントロールする」
といった小さなステップを作ります。 その一つひとつの過程を丁寧に踏み、ゆっくりと社会性を身につけていきます。
ABA(応用行動分析)

ABA(応用行動分析)では、お子様の行動を理解し、望ましい行動を増やし、問題行動を減らすための働きかけを行います。お子様一人ひとりのペースに合わせて、成功体験を積み重ねながら、自信と心の成長を促します。また、周囲の環境を整えることで、お子様がより良い行動ができるようサポートします。また、個人にのみアプローチするのではなく、周囲が工夫をして接することで、コミュニケーションや適切な行動を成立させることを重視します。
取り組みの例
お子様が、ぬいぐるみで遊ぼうとしたときに、遊びたいぬいぐるみを既に違うお友達が使っているのを見て、いきなりお友達からぬいぐるみを奪った。
この出来事についてABC分析を行うと次のようになります。
- A(事前の出来事): 使いたかったぬいぐるみをお友達が先に使っていた
- B(行動): 奪い取る
- C(行動の結果): ぬいぐるみで遊べた
対処法
1. 直接的支援
スタッフがサポートに入り、「貸して」「一緒に使おう」などの言葉でアプローチするなどの行動に置き換える。(適切な行動を増やして不適切な行動を減らしていく)置き換えができたら褒める。
2. 間接的支援
ぬいぐるみを使う順番などをあらかじめ決めておいたり、ぬいぐるみの数を増やしたりすることで、不適切行動が起きにくい環境をつくる。
運動療育

運動療育は、身体を動かす活動を通して、心身の成長を促すための療育です。姿勢を保ったり、バランスをとったり、あるいは身体全体を使って歩いたり走ったり、ジャンプしたりするような、粗大運動を中心に行っています。体幹を鍛えたりバランス感覚を身につけることは運動や言語機能向上に効果的です。平均台、ジャングルジム、マット運動、トランポリン、バランスボール、バランスストーン、ボルダリング、鉄棒、リズム体操などのいくつかの粗大運動を組み合わせた「サーキットトレーニング」を行っています。
取り組みの例
- 「運動しながら数えたり、指示に従ったりするなど、運動と認知を結びつける」
- 「五感を刺激し、心身をリフレッシュさせる」
- 「音楽に合わせて体を動かし、リズム感や身体の協調性を養う」